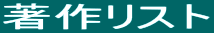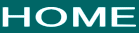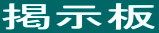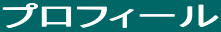月刊エッセイ 12/18/2002
■ 私は遅筆みたいだ
とうとう掲示板に書かれてしまった。本岡類は1年に1作くらいしか小説を発表しないからチェックするのが難しいが、これからはホームページを見ていれば新作がわかるので助かる、と。
まあ、こんなこと書かれるのも、仕方ないよなあ。計算してみると、18年間で30冊の本しか出していないんだから。なにせ、多作の作家は100 冊だ200 冊だといっているのに、私は30冊を青息吐息で書いている。こういう作家を世の中では“遅筆”と呼ぶらしいね。
遅筆というと、「うんしょ、うんしょ」と掛け声を発しながら、文字を一つ一つ書いているように見えるかもしれませんが、じつは、そういった部分もないわけではないのです。たとえば、自らを「遅筆堂」と称している井上ひさしさんの字は一点一画をおろそかにされておらず、原稿用紙には読み易い丸っこい文字がほぼ同じ大きさ並べられているんです。「憂鬱」の「鬱」の字などを書く時は、どのくらい時間がかかるのかと心配になるほどで、なるほど、この丁寧さでは締切りに間に合わなくなるのも無理ないなと思ったりもしました。
その昔、ある会合で、某新人作家が、
「僕は一日かかって5枚(400 字詰め原稿用紙)書くことにしてるんです」
と言ったのを受けて、速筆で知られる志茂田景樹さんが、
「えっ、石にノミで字を刻んでるんですか?」
と、からかっていましたが、半日で30枚書くと言われている志茂田さんにとっては、古代文明期の話のように感じられたのでしょう。
デビュー当時の林真理子さんと話していて、彼女が、
「わたし、一時間でだいたい7枚くらいの速度なんです」
と言ったので、びっくりしました。私はせいぜい2枚程度で、何も考えずに原稿を清書する時だって4枚がやっとだったのです。こうなってくると、どうもペンを動かす速度に格段の違いがあるらしい、うん、これは運動能力の違いなのかと思ったりもしたものです。
しかし、時は移って、今はほとんどの作家がキーボードを使う時代となりました。キーをぽんと打つと、字の上手い下手は関係なく瞬時に文字が現れるのですから、これは横棒や縦棒を引いたり、点を打ったりする速度とは関係ありません。キーを打つ速さの違いはあるでしょうが、プロは毎日原稿を打っているのですから、自然、キー・タッチは速くなります。つまりは、入力速度に大きな違いはないのに、一日の生産枚数が格段に違ってきている。
もってまわった説明は止めておきましょう。早い話が、遅筆と呼ばれている作家の多くは、きちんとした文章がとっとことっとこ頭に浮かんでこないから、キーを打つに打てないのです(たぶん。少なくとも、私はそうです)。もっとわかりやすく言ってしまえば、文才がない。
おいおい、プロ作家やってて文才はないというのはおかしいだろ、と思われる方もいらっしゃるでしょうが、じつは文才が不足しているプロというのは、けっこういるのです。なぜなら、小説を書くには、文章能力のだけでなく、発想力、ストーリー作りの能力、観察力など、多方面の力が必要で、劣っている文才を他の方面の能力で補うことも可能だからです。
とくにミステリーの場合、トリック作りとかストーリー・テーリングの能力がより重視されるため、文章能力が劣る人気作家も少なからず存在するのです。たとえば、70年代から80年代にかけて一世を風靡したMさんの小説は、私など読んでいるうち文章に悪酔いして、最後まで読み通せたことがありません。私もそういった文才がない作家の一人なのですが、その悪文を少しでも上手くしようと悪あがきするから、さらに筆は進まなくなります。
たとえば、「絶対零度」に出てくる下の文章(p 345)。
陽は閉ざされて、雲の向こう側にある太陽はぼんやりとした光のかたまりになっていた。標高が高いのか、塩田町よりも寒さを感ずる。右手の樹間に、白い煙を浮かべている浅間山が見えた。台状の頂きにこそ冠雪しているが、そこから下に続く部分は暗色の山肌が剥き出しになっている。周囲の木々に葉はなく、鳥の声は聞こえず、草には緑もなく、目はしだいに下ばかりを見るようになる。
何の変哲もない描写文ですけど、こうしたところが頭の中で上手く文章になってこない。で、二度三度と書き直すわけですが、文才がある人は、この程度の文はさらさらさらと書くんだろうなと、ただ羨ましく思うのです。
なぜ私には文才がないのか? 遺伝なのか、育った環境なのか? どうも両方みたいなんですな。じつは、うちの家系は男はほとんどが理科系(父方は父が獣医で、祖父が鉱山技術者。母方は叔父が大学の化学の教授で、祖父が海軍の造船技術者)で、文芸関係者は正真正銘のゼロ。自宅にあった子ども向けの本や雑誌も「科学大観」とか「日本の歴史」とか、科学性や論理性を重視するものばかりで、そんな書物を読んで育っているから、文芸的表現など身につける機会がまるでなかった。よく「家には文学全集が置いてあり、子供の頃から読んでいました」なんて言っている作家が多いみたいですが、そういう人は、作家になるローヤルゼリーを飲んで育っているというわけです。
私が作家になったのは、言ってみれば、突然変異みたいなものです。突然変異というのは、当人にとっては、けっこう辛いものがある。環境にフィットしていない遺伝子を持った生物が、何の脈絡もなしに登場してしまったわけですからね。
アイデアやストーリーを考えるのは大好きで、風呂に入って考えを巡らせているうち、いつの間にか2時間近くが経過していたり、ストーリーがどんどん膨らんで、手賀沼のまわりの遊歩道をあてどもなく歩きまわっていたなんてことも、たびたびです。しかし、いざ文章を書こうとすると、上手く言葉になってこないので、嫌さが先にたって、キーボードの前に座るのを少しでも遅らせようとする。この雑誌を読んでからにしようとか、洗濯してからにしようとか、いろんな用事を考えて、原稿書きを先延ばしにしているうちに、あーら、太陽はいつの間にか西に傾き、一日が終わりかけている。
私が子供の頃、同じ集落にイチクラさんという屋根屋さんがおったのです。イチクラさんは、暗くなっても、屋根の上まで電灯を引っ張って仕事をしている。一見、ものすごい働き者のように見えますが、事実は違って、その人、昼間はブラブラ遊んでるんですね。そして、周囲が暗くなり始めると、慌てて仕事にとりかかる。
「イチクラさんみたいになってはいけないよ」
母からは、そう言い聞かされて、私は育ってきたのですが、気づいてみると、私がそのイチクラさんになっている。今になって思えば、イチクラさんにはイチクラさんなりの事情があったのでしょう。上手く瓦を並べられないとか、日焼けして男前が台なしになるのが恐いとか(だったら、屋根屋になるなっての)……。
文才がないのに加えて、私には体力が欠けているという欠点もあります。集中して文章を書くというのは、けっこう体力を使うもので、私の場合は、1時間半から2時間ほど机に向かっていると、頭はぼんやりしてくるし、椅子に座っているのが辛くなってくる。
そうなると、ま、これだけ書いたからいいかと考え、リビングルームの安楽椅子でひと休みすることになる。すると、猫のセナが飛んできて、私の膝の上に乗り、丸くなります。猫好きの人にはわかるでしょうが、猫が気持よさそうに眠ってしまうと、それをのけるのは、気持の上で忍びがたい。
(まあ、もうちょっと寝かせておいてやるか……)
そう思って、膝の上に猫を置いておくうち、眠りというのは伝染するらしく、こっちもウトウトしてくる。ふと気づくと、2時間近くがたっている。昼近くから仕事を始めて、2時間ほど仕事をすると、2時間ほど猫を膝の上に乗せて居眠りをし、また2時間ほど仕事をして、2時間ほど猫つきで居眠りをし……
そんなことで、執筆がはかどるはずがありません。
さらに加えて、私にはADHDの傾向が多少あるようで、集中力が欠如していて……ああ、もう、止めにしておきましょう。仕事がはかどらない理由なんて、五つや六つは簡単に浮かびそうだ。
要は、私は何を言いたいのか? 要はですな、その、つまり、人には人それぞれの理由があるわけですよ。それを世間では「遅筆」だの「ナマケモノなんだ」だの「きっと才能がないんだよ」と勝手に評価を下して、ぶつぶつぶつ……。
しかしね、強火でささっと作ってしまう料理より、弱火でことこと煮込む料理のほうが、味が染みて美味い場合もあるのですよ。小説だって、筆が遅滞しているうち、内容が濃くなってくる場合もあるんです。
モーツアルトが35年の生涯で41曲も交響曲を作っているのに、ブラームスは64歳まで生きて、4つしか作っていない。でも、ブラームスをナマケモノという人はいないでしょ。好き好きだろうけど、ブラームスの交響曲4番はモーツアルトのどの曲よりも優れていると、私は思うんです。
でありますから、遅筆のどこが悪い? 寡作のどこが悪い? はは、今月は居直ってしまった。